院長 大内の考え
 院長 大内の考え
院長 大内の考え院長インタビュー
『クリニックのコンセプトと診療理念』
インタビュアー(以下、イ)
:本日は宜しくお願いいたします。
早速ですが、まずは、歯科の中でも矯正歯科を専攻された理由をお聞かせください。
大内仁守院長(以下、大)
:はい。不正歯列・不正咬合は先天的な因子のほか、後天的な要素も大きく関係する疾患です。しかし、疾患でありながら、直接的に生命に影響を及ぼしたり、すぐに悪化したりするような急性の病ではありません。そのため、歯並びや噛み合わせは、見た目の良し悪しの問題で片付けられてしまうことが、多いように感じます。
私は、歯並び・咬み合わせの重要性について正しく伝え、その上で、矯正治療が必要な患者の力になりたいと、歯科大学卒業後、歯科矯正講座に籍を置きました。
イ:たしかに、歯並び=見た目のために治す というイメージですね。
大:そう思われて、相談にいらっしゃる方が一番多いですね。もちろん、そのような考えでも、矯正治療を検討するきっかけとして十分意義があります。
しかし、見た目が良くなる以上に、結果として『健康な人生を歩む』ことにつながることを、ぜひ伝えたいです。
イ:『健康な人生』ですか?
大:矯正治療をすると、歯並びや口元、横顔などの見た目が美しく整います。と、同時に噛み合わせの機能も整って、しっかりと噛めるようになります。そうなると、食べ物の消化や栄養の吸収が良くなって全身のコンディションが上がったり、噛み合わせ由来の偏頭痛や肩こり、顎の痛みが改善したりと、日常生活が快適に過ごせ、健康な人生に繋がっていきます。
イ:なるほど。歯並び・噛み合わせの良し悪しは、見た目の問題で収まらない、健康を維持する上で、重要な要素の一つなのですね。
大:はい。ちなみに、8020運動というものをご存知ですか。
イ:80歳になっても自分の歯を20本残すことを目指す、健康目標ですよね。
大:そうです。「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」との願いが込められています。80歳で20本自分の歯があれば、食生活にほぼ満足することができると言われています。
実際に8020を達成されている方は、ほぼ例外なく良い歯並び・噛み合わせをされています。しっかり噛んでいる歯は、噛む力がうまく分散されるので、1本に過重な負担がかからず、歯の寿命が長くなります。また、歯垢も溜まりにくく歯磨きもしやすいので、虫歯や歯周病などのリスクを下げられ、それらが起因の抜歯も減らすことができます。
ご高齢の方の八重歯や受け口の笑顔って、イメージできますか?
イ:…イメージしにくいです。
大:そうだと思います。お年寄りの笑顔=きれいに並んだ歯が見える笑顔、ではないでしょうか?
イ:たしかに。
大:そこで見えているのは、歯並びが整っている自分の歯か、義歯のどちらかでしょう。デコボコの歯並び、受け口や出っ歯のお年寄りは多くありません。それは、その年になるまで、良くない歯並び・噛み合わせを維持できなかったから。咬んでいない歯は寿命が短いのです。
イ:健康な人生を歩んだ先に、8020が達成され、いつまでも美味しく満足のいく食事が出来る。生涯にわたって、整った歯並びというのはとても価値があるように思います。
イ:続いて、クリニックを開業された経緯についてお伺いしたいのですが、こちらは矯正歯科専門のクリニックでありながら、小児歯科も併設されています。その理由をお聞かせください。
大:はい。ここで突然ですが、自分の子供の歯並びについて、“矯正治療をした方が良いかな”と考え始めるのは、どのようなきっかけがあってだと思いますか?想像で構いません。
イ:そうですね…子供だったら、学校検診で引っかかったら、でしょうか。もう少し大きい子だったら、本人が気にしていたり、治療したいと言ってきたりしたタイミングで、考え始めると思います。
大:そうですよね。自分では気付かなかったけど、誰かに言われて初めて気づく、考えるきっかけになることは、歯並びに限らず、結構あると思います。
検診で指摘されたタイミングで矯正相談にいらっしゃる方は、決してタイミングを逃していません。検診結果をそのまま放置されてしまうより、ずっと良いです。でも、全員がそのタイミングが矯正治療開始のベストだったかというと、そうでもありません。
イ:ベストタイミングは、そこではないということですね。
大:学校検診は大抵、年1、2回で校医も交代します。一人ひとりの経過を追って把握していることも、ほぼありません。その時点の状態だけで結果を出さなくてはならないのです。
でも、もし、赤ちゃんの頃から定期検診で通っている歯医者さんだったらどうでしょうか。乳歯の生え始めから、乳歯列の完成、抜け替わりと、経過を丁寧に追えますし、ご両親やご兄弟の歯並びとの関連、各ご家庭の事情なども把握できます。その中で、まだ幼くても「上下の噛み合わせが少し心配だから、検診のタイミングで経過を見ます。」とか、「早めの治療が必要」「永久歯に生え変わってからのタイミングで、検査しましょう」など、こちらも先を見据えたアドバイスができますし、親御さんもお子さんも、『いずれは、矯正治療する必要がありそう。』と、気持ちの準備ができるのです。この気持ちの準備が、矯正治療のハードルを低くし、スタートをスムーズにしてくれます。学校検診が“急に言われて”なのに対して、こちらは“予告済み”。ずっと受け入れやすいと思いませんか?
イ:そうですね!子供も、ずっと通っている歯医者さんだったら安心できますし、矯正治療を特別に感じなさそうです。親の立場で言えば、気持ちの準備があることで、金銭面の準備も計画が立てやすくなりますね。矯正治療は、高額なイメージがあるので…
大:そうですよね。保険診療でないので、高額ではあります。料金設定も、地域や立地によって幅があったり、治療費は低めでも、毎回の処置料の支払いがあったりすると、治療期間によってはトータルでかなり高くなってしまう場合もあります。
イ:治療期間は、経過が患者側では予測出来ない分、負担になってしまいそうですね…
大:はい。長くかかればその分お金もかかってしまう。そうなると、『もう終わりにしたい。』という気持ちが生じてしまって、治す側としてはまだ完全な状態ではないけれど、早く終わらせるための妥協点を見つけなくてはならなくなる…金銭面の事情も非常に大事ですから。
でも、患者さんも、決して中途半端な治療で終わりたいはずはないですし、こちらもプロとして納得いくまでとことん治療したい。そのために、当院ではトータルフィー制度を採用しています。
イ:トータルフィーとは、どのようなシステムですか?
大:診断時にご提示する治療費のみのお支払いで完結し、毎回の処置料のお会計はありません。治療期間が当初の計画より延びたとしても、予約通りに通院を続けている場合には、追加料金が発生したりもしないので、双方が納得いくまで治療を続けることが出来ます。
お金を持たせなくて良いので、お子さんが一人で通院する際、保護者の方も安心かと思います。また、『矯正のワイヤーが引っかかって痛い』とか、『装置が合わない』などの緊急時の来院でも同様ですので、予約さえしていただければ、処置料が勿体ないからと痛みを我慢することなく、来てもらって構いませんし、お手持ちが無くても、わざわざお金を取りに一旦帰る必要なく、学校や仕事帰りにそのまま立ち寄っていただけます。
(※緊急時も要予約。破損や紛失などの修理・再製作は規定の料金が発生します。)
イ:それはとても助かりますね!
イ:続いて、最近急増しているマウスピース矯正についてお聞かせください。マウスピース矯正は、一般の歯科でも出来る所が増えています。こちらのクリニックでも、インビザライン矯正を取り入れられていますよね。
大:はい、10年以上前から取り入れており、症例を重ね、日々、治療精度と仕上がりの向上を図っています。
イ:精度や仕上がりは、どのクリニックで誰が行っても、一律にしっかり治るわけではないのですか? 製作元が同じ、使う製品が同じでも、差が生じてしまうのでしょうか?
大:処方、管理する歯科医師が、歯科矯正の知識を持っているか、マウスピース矯正の特性を十分理解しているか。それで、大きく違ってきます。
イ:『ただ、はめていれば治る。』というわけではなさそうですね…
大:そう思っている歯科医師が取り扱っているケースが増えており、危機感を持っています。実際に、矯正の知識がないまま治療を始め、治らず、トラブルに発展した事例もあります。
一般歯科のクリニックでは、矯正治療を日常的に行っていないことが多いので、患者は他の矯正歯科でしっかり治さなくてはならないでしょう。気の毒としか言いようがありません。
虫歯治療で通っている歯科でついでに矯正もできるなら、患者さんとしては気軽でありがたいと感じるかもしれませんが、きちんと治るのか、それまでに治った患者はどのくらいいるのか、もし経過が芳しくない場合の手立てや補償はあるのかなど、安心して任せられることが確信できるまで、情報を集めて検討して欲しいと思います。
イ:そうですね。“こんなはずでは無かった“と後悔しないためにも、マウスピース矯正であっても、十分な矯正の知識と実績のあるクリニックで行うのが最善のようですね。
大:矯正専門のクリニックであることが、絶対条件ではないでしょうか。マウスピース矯正は、衛生面や口腔内の違和感の少なさにおいて優れていますが、奥歯が上下で離開して接触しない、噛まなくなりやすいという、悪い面もあります。いくら上下それぞれの歯並びが完璧に並んでも、それらが緊密に噛み合わせられなければ機能しません。
当院ではマウスピース治療の途中や最終段階で、必要と判断した場合、患者さんと相談しワイヤー矯正へ切り替えるなどして、機能面もきちんと整えてから治療を終えます。患者さん側としては、ワイヤーをつけることは不本意でしょうし、マウスピースだけで治したい気持ちでいっぱいだと思います。しかし、『出来ないことは出来ない、だからここから先は、こういう方法で治していきます。』ときちんと示し、完遂することが、矯正治療を行う者としての責任だと考えます。
イ:健康な人生に繋がる大切な歯並び・噛み合わせですから、治しきる責任をもって治療に取り組まれているのですね。本日はお聞かせいただき、ありがとうございました。
院長 大内の考え
私は、人の歯が一生涯しっかりと噛めるように、そして虫歯に悩まされることなく健康に過ごせるようにとの思いを込めて、日々の治療に取り組んでいます。
歯列不正は、虫歯や外傷のように痛みを伴ったり、食事ができなくなるような急性の症状があるわけではありません。歯並びが悪くても、すぐに命に関わるような問題になることはないのです。有史以来、「歯並びが悪くて命を落とした人」はおそらく一人もいないでしょう。
しかし、私たちはその歯をいつまで使うつもりなのかを真剣に考える必要があります。
「歯はどうせ虫歯になって抜けてしまうものだから、そのときに入れ歯やインプラントにすればよい」と考えるのか。
「先のことは気にしない」という人生観を持つのか。
それとも、「できるだけ自分の歯を大切にし、長く使えるようにできる手は打っておきたい」と考えるのか。
おそらく、若い今のうちは「歯を失う苦労」を現実的に想像するのは難しいと思います。
私自身もそのつらさを実体験したわけではありません。ただ、総入れ歯だった祖母が「入れ歯だけにはなるもんじゃない」と、顔を合わせるたびに口にしていたことが、強く心に残っています。きっと大変な思いをしていたのでしょう。
「80歳になっても20本以上の歯を残す」という治療目標があります。
実際に、そのような方々のお口の中を調べてみると、共通して次のような特徴がありました。
・歯並びが整っている
・噛み合わせが安定している
・虫歯治療の痕跡が少ない
また、八重歯のおじいちゃんやおばあちゃんがほとんどいないことからも、歯並びの良さが長寿と歯の健康に直結していることは間違いないと考えています。
つまり、自分の歯を長持ちさせるために大切なのは:
歯列を整え、食べかすが詰まりにくく清掃しやすい口内環境をつくること
噛み合わせを正しくし、噛んだときの力が偏らず、多数の歯に分散されるようにすること(局所的な過重負担は、歯の寿命を縮めます)
日頃の自己メンテナンスを徹底し、なるべく虫歯や歯周病で歯科にかからないようにすること
歯並びの良し悪しは、生まれ持った要素や成長環境によるものであり、自分の努力だけではどうにもならないことも多いです。
だからこそ、矯正治療によって正しい状態に導いてあげることが、自分の歯で一生噛める環境づくりにつながり、ひいては人類の福祉への貢献になると私は考えています。
抜歯に対する考え方
私は、患者さんに対して抜歯を推奨することは決してありません。
しかし、治療方法をご説明する際には、選択肢の一つとして「抜歯を伴う矯正治療」を含めてお話しすることがあります。
あくまでもそれは、治療上の必要性がある場合に限ったことであり、抜歯が選択肢となるのは基本的に二次(本格)矯正治療におけるケースです。
一次矯正の場合において、永久歯を抜くことはまずありません。
大切なのは、「抜かないと治らないのか」「抜いてしまって本当に大丈夫なのか」という、治療の目的と長期的な結果を見据えた判断です。
一般的に、抜歯が必要とされる理由には以下のようなものがあります:
歯の“押しくらまんじゅう”状態(叢生)が強く、抜歯によってスペースを作らなければ歯をきれいに並べることができない場合
叢生がそれほど強くなくても、非抜歯では上下の噛み合わせがしっくり合わない場合
歯が並び、噛み合わせも一見良好であっても、顔貌とのバランスを考えたときに非抜歯では調和の取れた仕上がりが得られにくい場合
統計的にも、すべての歯が揃っていても噛み合わせが良くない状態より、必要な抜歯を行い噛み合わせや顔貌との調和を図ったケースの方が、歯の寿命が長く、咀嚼効率(食物をどれだけ細かく噛み砕けるか)も高くなることがわかっています。
ある患者さんから「残したくても残せない人がいる中で、健全な歯を抜くのはいかがなものか」というご意見をいただいたことがあります。
たとえば、事故などで不幸にも歯を失った方がいれば、それは本当にお気の毒なことで、深くお悔やみ申し上げるしかありません。
しかし、本来であれば残せたはずの歯を、何の対策もせずに放置してしまったために失ったというのであれば、それは「もっと早く手を打っておくべきだった」と考えざるを得ません。
その「早く打てる手」のひとつが矯正治療であり、矯正治療の中には、抜歯を伴うことで結果的に歯を守る選択肢があるのです。
結論として、抜歯を行うか否かは、それぞれのメリット・デメリットを患者さんおよびご家族としっかり話し合った上で判断すべきだと私は考えています。
大切なのは、「なぜその選択をするのか」を理解し、納得したうえで治療に臨むことです。
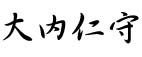
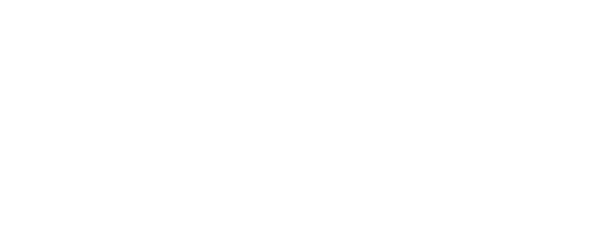
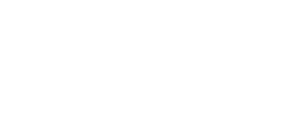


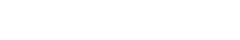
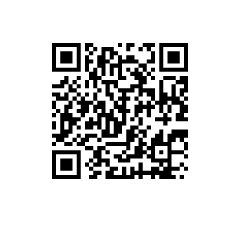
 Instagram
Instagram